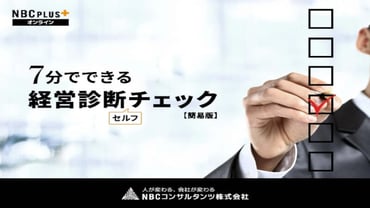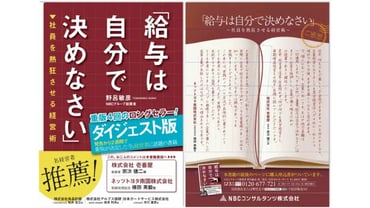メディアでも大きく取り上げられた『老後資金2,000万円問題』。
この言葉が独り歩きしてしまった理由は日本人の金融リテラシーの低さが原因といわれています。
今回は金融リテラシーについてのクイズを5問掲載していますのでぜひ自分の金融リテラシーをチェックしてみてください。
目次
日本人は金融リテラシーは低い?
メディアでも大きく取り上げられた『老後資金2,000万円問題』。
メディアや街行く人々からは「20歳から社会保険料を払い続けてもなお、2,000万円必要なのか?」というネガティブな意見が多かったように思いますが、この言葉が独り歩きしてしまった理由は日本人の『金融リテラシー』の低さにあるといわれています。
金融リテラシーとは、お金に関する知識・判断力のことです。日本では、お金に関する話はなんとなくしてはいけないような風潮があり、家計管理をはじめとする金融教育はほとんど行われていません。
また、リスクを嫌う日本人は、金融資産の半分以上を利息がほぼつかない銀行口座に預けています。
物価は年々上昇するも、これではお金は当然増えていきません。
さらに、ほとんどの日本人は、社会保障に関してあまり知識がなく無頓着にもかかわらず、年金に不満や不安を抱いています。
金融リテラシークイズ
ここで、金融リテラシーに関する簡単なクイズを紹介します。ご自身の理解度を確認してみてください。出所:『金融リテラシークイズ』金融広報中央委員会『知るぽると』
【問1】家計の行動に関する次の記述のうち、適切でないものはどれでしょうか。
1.家計簿などで、収支を管理する。
2.本当に必要か、収入はあるかなどを考えたうえで、支出をするかどうかを判断する。
3.収入のうち、一定額を天引きにするかなどの方法により、貯蓄を行う。
4.支払を遅らせるため、クレジットカードの分割払いを多用する。
【問2】一般に「人生の3大費用」といえば、何を指すでしょうか。
1.一生涯の生活費、子の教育費、医療費
2.子の教育費、住宅購入費、老後の生活費
3.住宅購入費、医療費、親の介護費
【問3】金利が上がっていくときに、資金の運用(預金等)、借入について
適切な対応はどれでしょうか。
1.運用は固定金利、借入は固定金利にする。
2.運用は固定金利、借り入れは変動金利にする。
3.運用は変動金利、借入は固定金利にする。
4.運用は変動金利、借入は変動金利にする。
【問4】10万円の借入があり、借入金利は複利で年利20%です。返済をしないとこの金利では、何年で残高は倍になるでしょうか。
1.2年未満
2.2年以上5年未満
3.5年以上10年未満
4.10年以上
【問5】金融商品の契約についてトラブルが発生した際に利用する相談窓口や、制度として、適切でないものはどれでしょうか。
1.消費生活センター
2.金融ADR制度
3.格付会社
4.弁護士
<正解>【問1】4【問2】2【問3】3【問4】2【問5】3
いかがでしょうか?簡単でしたか?
日本人の平均点(2019年度)は、52.8点です。
このクイズには、金融の知識が問われるものだけではなく、家計管理や生活設計に関する設問も含まれています。金融リテラシーというと金融資産の運用に関わる知識に関心が集まりがちですが、生活設計や家計管理の部分が非常に重要です。
金融庁の金融審議会「市場ワーキング・グループ」の報告書でも、下記のような記載によって個々人で生活設計を考え、対応していくことの重要性を説いています。
このようにライフスタイルが多様化する中では、
個々人のニーズは様々であり、
大学卒業、新卒採用、結婚・出産、住宅購入、定年まで
一つの会社に勤め上げ、退職後は退職金と年金で収入を賄い、
三世帯同居で老後生活を営む、というこれまでの
標準的なライフプランというものは多くの者にとって
今後はほとんどあてはまらないかもしれない。今後は自らがどのようなライフプランを想定するのか、
そのライフプランに伴う収支や資産はどの程度になるのか、
個々人は自分自身の状況を「見える化」した上で
対応を考えていく必要があるといえる。
老後資金として2,000万円が不足との報道に国民が不安をつのらせた理由の一つは、生活設計ができていないことにあるのです。
理想とする生活設計を実現するためには経済面を軸に置いて計画を立てていかなければなりません。
その他関連記事
この記事の著者
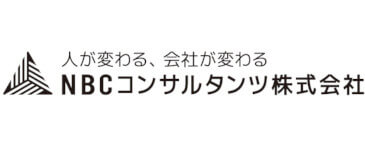
NBCコンサルタンツ株式会社
NBCコンサルタンツ株式会社は1986年の創業以来、会計事務所を母体とする日本最大級のコンサルティングファームとして数多くの企業を支援しております。4,290社の豊富な指導実績を持つプロの経営コンサルタント集団が、事業承継、業績改善、人材育成、人事評価制度など各分野でのノウハウをお届けします。